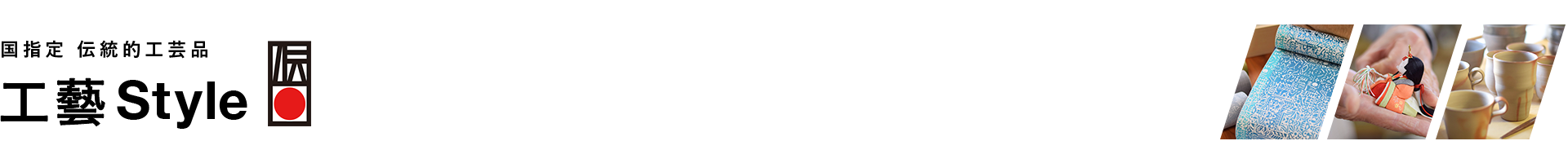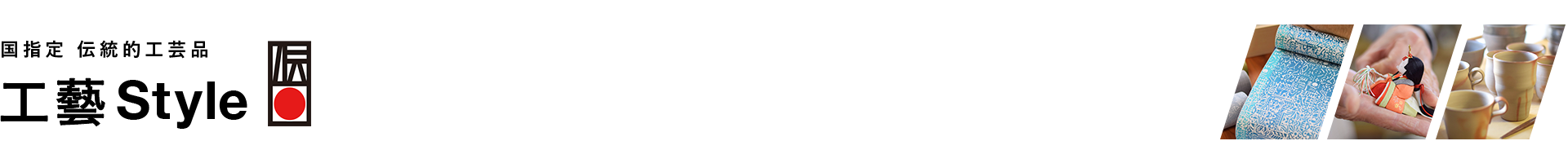有松・鳴海絞
絞の技法そのものは、奈良時代に始まったものですが、有松・鳴海絞が始められたのは、江戸時代の初め頃です。
現在の大分県にあたる豊後の大名が、名古屋城築城の手伝いを命ぜられた時に、豊後から連れて来た人たちによって、技法が伝えられたと言われています。
その後、現在の愛知県を治めていた尾張藩の保護のもとに行われた、たゆまぬ努力によって、絞独特の上品で多種多様な技法が考案、開発され、現在に至っています。
概要
| 工芸品名 |
有松・鳴海絞 |
| よみがな |
ありまつ・なるみしぼり |
| 工芸品の分類 |
染めもの |
| 主な製品 |
着物地、羽織、浴衣(ゆかた) |
| 主要製造地域 |
名古屋市、岡崎市、半田市、刈谷市、知多半島他 |
| 指定年月日 |
昭和50年9月4日 |
特徴
木綿絞の代表産地で、絞の技法は100種にも及び、多彩な文様が表現されています。最も代表的な絞技法には縫絞(ぬいしぼり)、くも絞、三浦絞、鹿の子絞、雪花絞(せっかしぼり)等があります。藍染めの絞には、絞りのときに出来る濃淡に、独自の風合いがあります。
作り方
図案どおり型紙を彫り、絹、綿等の布に下絵刷をして、その布を糸で括(くく)り、染め上げます。糸で括られた部分には染料が乗らないため、糸抜きをすると様々な模様が浮かび上がります。なお、これらの作業はすべて分業化されています。