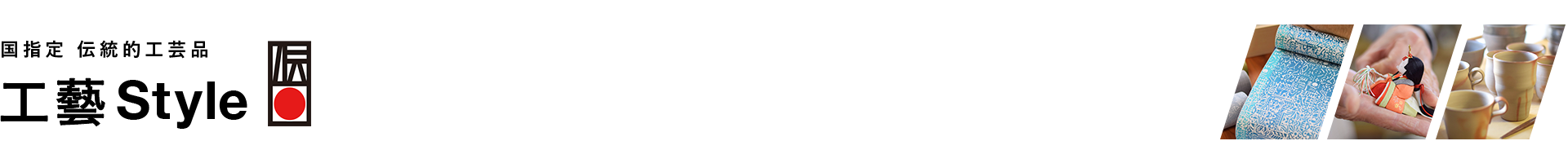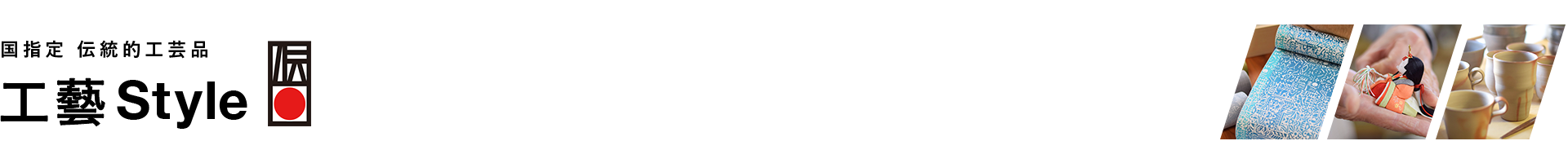知花花織
古くから、旧美里村(現在の沖縄市の知花、登川、池原等の地域)で盛んに織られていた知花花織は、経浮花織の技法を駆使した紋織物の一種で、19世紀後半には既に技術・技法が確立し、明治時代以降も祭事用のウッチャキ(上着)、ティサージ(手巾)、ドゥジン(胴衣)、着物などが織り続けられていました。第二次世界大戦で壊滅的な打撃を受けましたが、知花花織の衣装は、五穀豊穣や無病息災を祈願する伝統行事(ウスデーク)で、現在も着用されています。
概要
| 工芸品名 |
知花花織 |
| よみがな |
ちばなはなおり |
| 工芸品の分類 |
織りもの |
| 主な製品 |
着物地、帯、羽尺、小物 |
| 主要製造地域 |
沖縄市 |
| 指定年月日 |
平成24年7月25日 |
特徴
模様を出した際に、布の裏の経糸が浮いているのが特徴です。
作り方
技法的には二種類あり、花綜絖を使用する綜絖花技法と、花綜絖を使用せずに紋糸を手ですくい取る手花技法があります。①綜絖花(ソーコーバナ)技法は、花糸(紋糸)が経糸方向に浮く二重織の織物で、紋の柄出しは、図案に従って花綜絖枠を順次手で持ち上げてフックに掛けながら製織します。布面の表情では、布表の柄模様が経糸方向に浮いており、布裏は組織されていない紋糸が遊び糸として経糸方向に長く走っています。②手花(ティーバナ)技法は、文様部分の経糸を手ですくい取るために縫い取り織とも呼ばれています。布表の柄文様は、経糸方向あるいは緯糸方向に浮いており、布裏はソーコーバナとは異なり、組織されていない遊び糸が大きく走ることはありません。