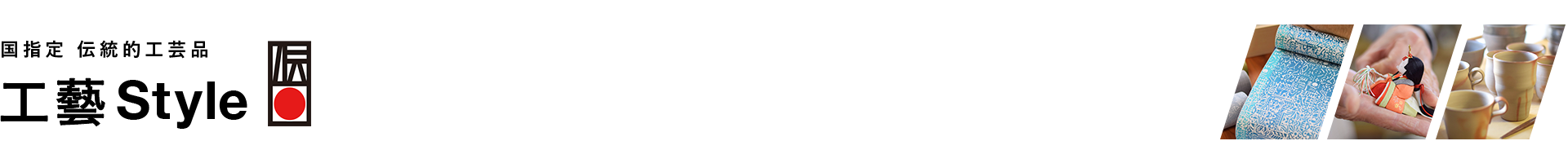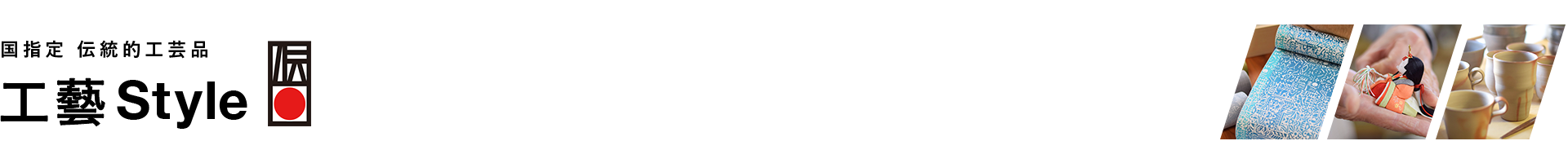本場大島紬
奄美における大島紬の始まりは、7世紀頃に遡ります。産地が形成されたのは18世紀初期のことで、その後、技法は鹿児島にも伝わりました。絣模様は締め機(しめはた)という独特の機を用いて作られます。糸を染める「泥染め」の技法は特に有名です。
紬のルーツは、遠くインドでうまれたイカットという絣織り(かすりおり)だと言われており、イカットが、スマトラ、ジャワからスンダ列島一帯に広がりを見せた頃に、奄美大島にも伝わったと言われています。
概要
| 工芸品名 |
本場大島紬 |
| よみがな |
ほんばおおしまつむぎ |
| 工芸品の分類 |
織りもの |
| 主な製品 |
着物地 |
| 主要製造地域 |
奄美市、鹿児島市、大島郡竜郷町、喜界町、宮崎県/都城市他 |
| 指定年月日 |
昭和50年2月17日 |
特徴
繊細でしかも鮮やかな独特の美しい絣模様、そしてシャリンバイと泥染めによるしぶい風格、しなやかで軽く、しわになりにくい、奄美の自然から生まれた、人に優しい織物です。
作り方
原図から図案設計され、それをもとに絣締(かすりじめ)をし、シャリンバイと泥で染色した後、これをほどいて加工を行い、最後に製織が行われます。全工程には約半年から1年かかります。