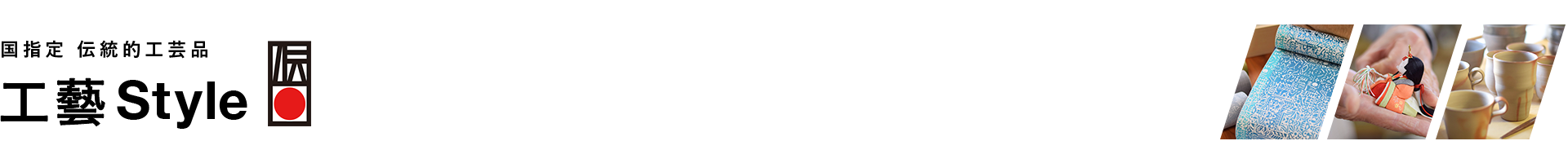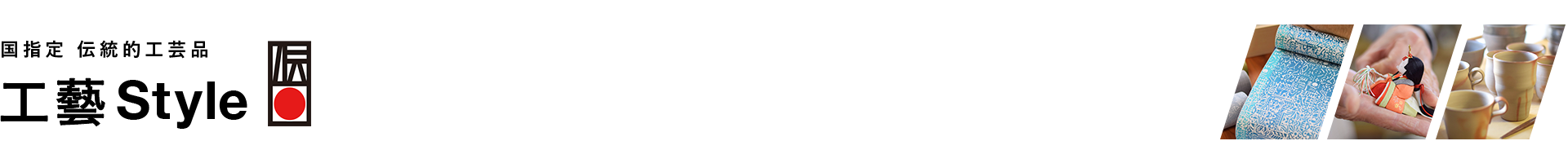加賀友禅
加賀友禅の始まりは、加賀独特の染め技法である「梅染(うめぞめ)」まで遡ります。「梅染」は15世紀の中頃には、すでに存在していたことが文献に記されています。
梅染のほか「兼房染(けんぼうぞめ)」、「色絵紋」等の染色技法が古くから加賀に伝えられており、これらを総称して「お国染」といいました。この加賀お国染の技法を基礎に、江戸時代中期に、宮崎友禅斉が絵画調の模様染めを指導したところから、加賀友禅が確立されました。宮崎友禅斉は京都で友禅染を始めた人物で、金沢で晩年を過ごし、友禅の指導を行ったと言われています。
概要
| 工芸品名 |
加賀友禅 |
| よみがな |
かがゆうぜん |
| 工芸品の分類 |
染めもの |
| 主な製品 |
着物地、帯、小物 |
| 主要製造地域 |
金沢市 |
| 指定年月日 |
昭和50年5月10日 |
特徴
加賀友禅の特徴は、落ち着きのある写実的な草花模様を中心とした絵画調の柄です。加賀百万石と言われた豊かな前田家の文化的な趣味を強く反映して、渋さの中にも武家風の気品を漂わせています。
作り方
正絹白生地に「藍花」による下絵を施し、糸目糊置(いとめのりおき)で防染し、化学染料・顔料を用いて手描彩色します。地染の後、蒸気で蒸して染料を定着します。最後に、余分な染料や防染糊等を落とすために水洗いします。別の技法として、型紙を用いて写し糊で捺染(なっせん)をする、板場友禅もあります。