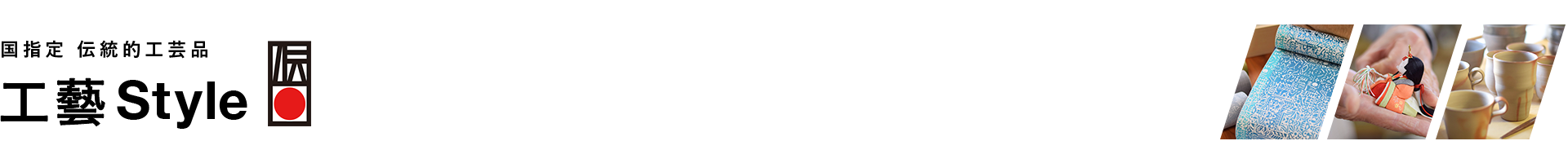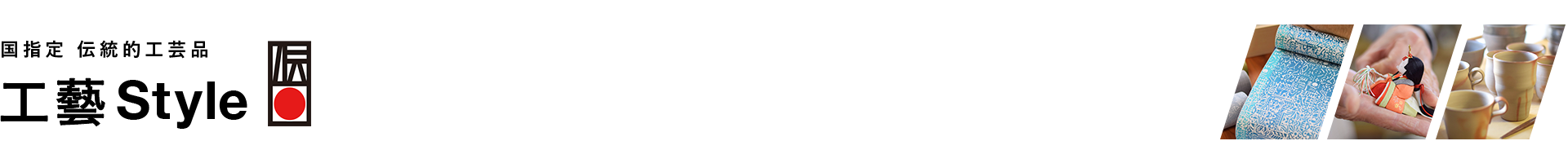笠間焼
笠間焼は江戸時代の中期に箱田(現在は笠間市内)の職人が信楽焼の陶工の指導で窯を焼いたのが始まりとされています。明治時代に廃藩置県で笠間藩がなくなるまで、藩の保護・奨励を受けていました。
笠間焼が生まれてから昭和20年代頃までは、瓶や摺鉢等の台所用品が多く焼かれていましたが、少しずつ作られる製品の種類が変わって、現在では食器等の食卓用品や花瓶や置物等が作られるようになりました。
概要
| 工芸品名 |
笠間焼 |
| よみがな |
かさまやき |
| 工芸品の分類 |
陶磁器 |
| 主な製品 |
洋食器、和食器、花器、置物 |
| 主要製造地域 |
笠間市、水戸市、石岡市、常陸太田市、ひたちなか市、筑西市他 |
| 指定年月日 |
平成4年10月8日 |
特徴
笠間焼には、200軒ほどの窯元や、陶芸作家、販売店があります。主として手作りの製品で個性的なものや、これまでになかった新しい感じのするものから伝統的なものまで、色々な感性の作品が共存する特異な産地として注目をあびています。
作り方
笠間焼は、原料の陶土に鉄分が含まれているため、そのままだと赤黒い陶器になります。そこに絵付けや、白い土を水で溶かしたものを使って飾りを施すことで、色々な表情のある作品を作り出しています。作り方は手作りで、ろくろ、たたら、ひねりだし等の方法で作ったものが多く見られます。