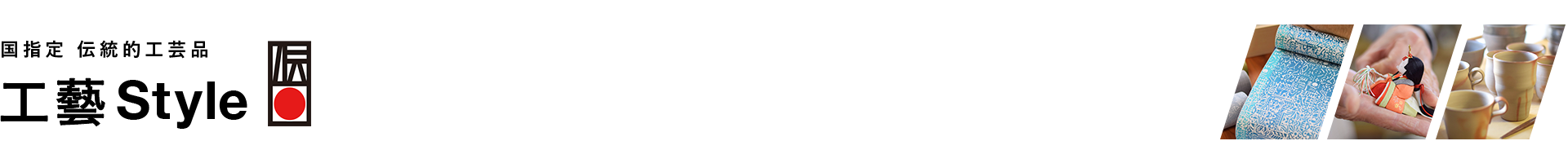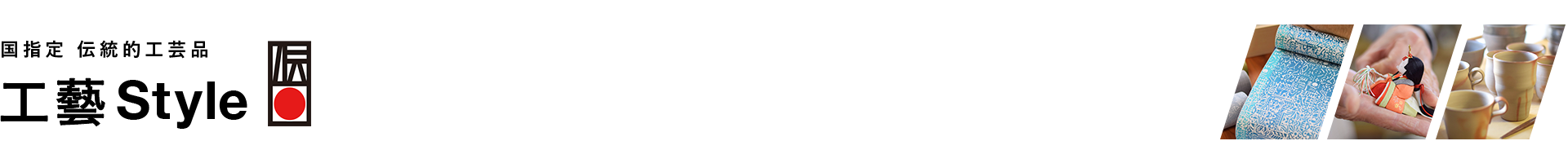京指物
始まりは平安時代に遡ります。室町時代以後には専門の指物師が現れ、茶道文化の確立とともに、京指物も発展しました。
無垢板(むくいた)を用いた高級和家具の調度指物と、キリ、スギ、クワ、ケヤキ等の木の素材を生かした挽物(ひきもの)、曲物、板物等の茶道具指物があります。
概要
| 工芸品名 |
京指物 |
| よみがな |
きょうさしもの |
| 工芸品の分類 |
木工品・竹工品 |
| 主な製品 |
箪笥、飾棚、茶道具 |
| 主要製造地域 |
京都市 |
| 指定年月日 |
昭和51年6月2日 |
特徴
京指物は、桐製品に代表されると言えます。桐材は水気を防ぎ、熱にも強いことから、桐製品は収納調度の高級品の代名詞となっています。京指物で使う桐材は、長い自然乾燥、アク抜きといった素地作りに心を配っています。
作り方
木目の自然な風合いを基調とする京指物の仕上げの基本は、良材の美しい木目をそのまま活かした木地仕上げです。木地仕上げには、研ぎ仕上げ、蝋(ろう)拭き仕上げ、着色蝋拭き仕上げ、摺(す)り漆仕上げがあり、加飾には蒔絵、漆絵、彩絵、箔、金銀泥、砂子その他を用いています。