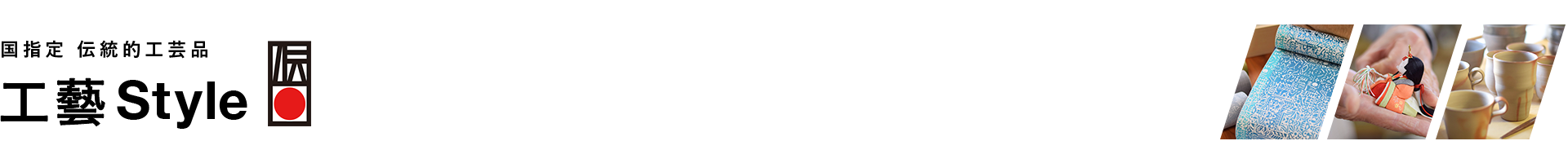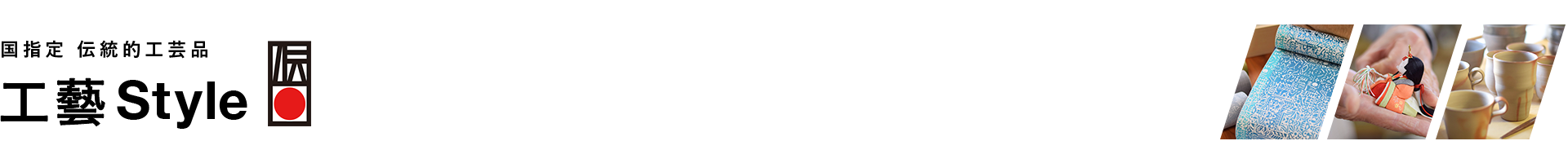小千谷紬
江戸時代中期に始まった養蚕とともに紬織物は始められました。江戸時代後期には、現在の群馬県にあたる上州や京都等の織物の盛んな所から生糸商人が商談に訪れるほどの産地でした。
くず繭を使った紬は自家用として織られたもので、小千谷縮の技法が使われていました。紬織物は小千谷縮に隠れた存在でしたが、昭和の初期には本格的に紬の生産が始まりました。紬糸に改良を重ねて、現在の紬織物の基本が出来ました。
概要
| 工芸品名 |
小千谷紬 |
| よみがな |
おぢやつむぎ |
| 工芸品の分類 |
織りもの |
| 主な製品 |
着物地、室内インテリア |
| 主要製造地域 |
長岡市、小千谷市、十日町市 |
| 指定年月日 |
昭和50年9月4日 |
特徴
紬に用いる糸は、繭を綿状にしてから作られるため、糸に膨らみがあり、軽く暖かな織物が出来ます。民芸調の柄が色々あり多彩なおしゃれが楽しめます。
作り方
繭を裂き、綿状にしてから糸にして紡(つむ)ぎ、真綿の風合いを出します。柄模様は、織る前の糸に木羽定規(こばじょうぎ)を合わせて、糸に直接染料を摺(す)り込みます。色止めの後、織幅の端の目印となる「耳じるし」を合わせながら織ります。