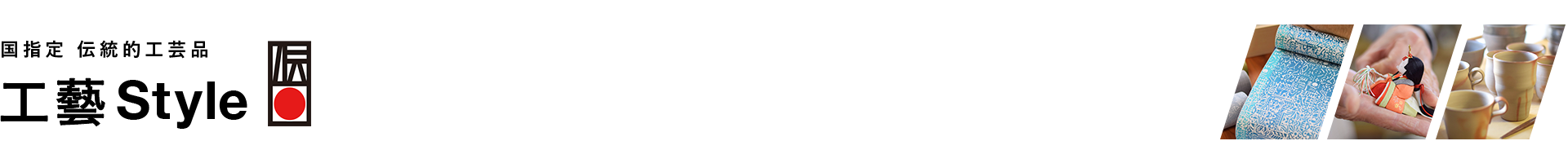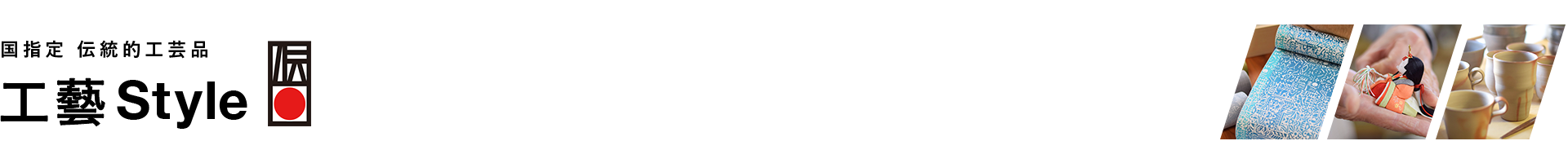琉球びんがた
琉球びんがたの始まりは、15世紀中頃にまで遡ることができます。
琉球びんがたは王府の手厚い保護の下で生産され、19世紀初めの歴史書には琉球の紅型(びんがた)が東洋花布と称され、福建市場において名高い貿易品であったことが記されています。
第2次大戦により壊滅的な打撃を受けましたが、戦後、紅型保存会の結成、沖縄びんがた伝統技術保存会の結成、昭和59年の国の「伝統的工芸品」の指定を経て、その振興が図られています。
概要
| 工芸品名 |
琉球びんがた |
| よみがな |
りゅうきゅうびんがた |
| 工芸品の分類 |
染めもの |
| 主な製品 |
着物地、帯、飾布 |
| 主要製造地域 |
那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、豊見城市 |
| 指定年月日 |
昭和59年5月31日 |
特徴
中国の型紙の技法、京友禅の手法も取り入れた沖縄で唯一の染物です。綿布、絹布、芭蕉布等に顔料、植物染料を用いて手染めします。色鮮やかな「紅型(びんがた)」と琉球藍の浸染(しんせん)による「藍型(えしがた)」とがあります。それぞれ南国独特の神秘的な魅力を持っています。
作り方
技法によって「型付け(型染め)」と、型紙を用いず生地に下絵を描き、糊袋の筒先で下絵の上から糊を置き、その後彩色する「筒引き(筒描き)」とに分かれます。また、色調には「紅型」と「藍型」があります。型紙は、柿渋を用いて手漉(す)き和紙を貼り合せた地紙の下にルクジュをあてがい、下絵にそって小刀で凸彫りします。染色の際、模様の部分に色挿(さ)しをし、その上に隈取りというぼかし染めが施され、立体感を表現します。