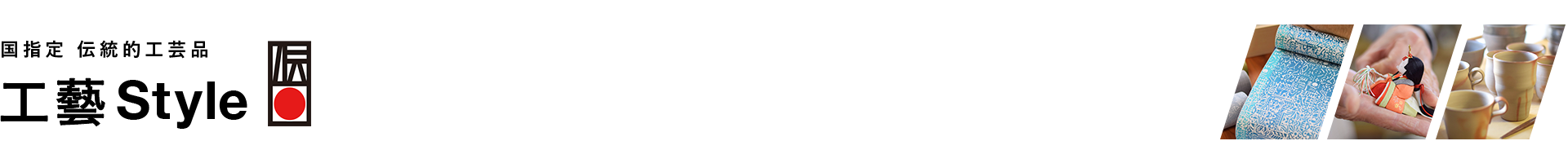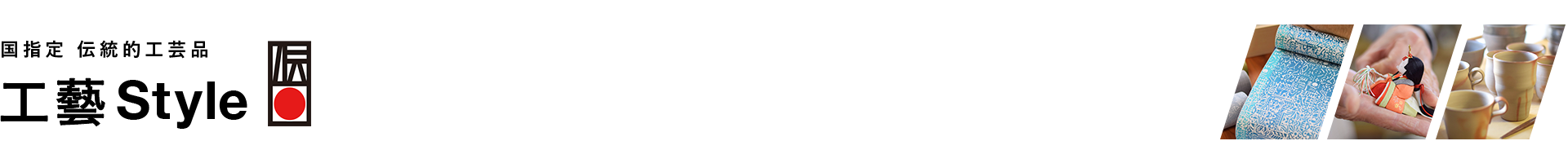内山紙
内山紙の始まりは、江戸時代初期に、美濃で製法を身に付けた職人が、自分の家で漉(す)いたのが始まりと言われています。
内山紙の名はその地名から付けられたものです。多量の雪でコウゾを晒(さら)して白くする「凍皮」、雪晒し等、独特の技術を作り上げました。
概要
| 工芸品名 |
内山紙 |
| よみがな |
うちやまがみ |
| 工芸品の分類 |
和紙 |
| 主な製品 |
障子紙、永年保存用紙、加工書道用紙、紙加工品、一〆張り |
| 主要製造地域 |
飯山市、下高井郡野沢温泉村、下水内郡栄村 |
| 指定年月日 |
昭和51年6月2日 |
特徴
原料はすべて和紙原料の中で最も強くしなやかなコウゾを使用し、パルプは使用していません。コウゾ100%の紙は強靱で、通気性、保湿力に優れています。日に焼けず、強靱で長持ちするため障子紙としては最適です。また、長期間にわたって保存するための紙としても優れています。
作り方
コウゾの原木から内山紙が出来るまでには20~25くらいの工程があります。良質な内山紙を作るためには原料の下準備、紙漉き、乾燥の工程が大事です。とくに紙漉き作業は紙の良し悪しを決める大切な作業です。「流し漉き」は、手の切れるような冷たい水の中で少しも手を止めることなく、常に前後左右に動かし続け、紙の表情を作ります。漉きやすくするための水作りも大切です。