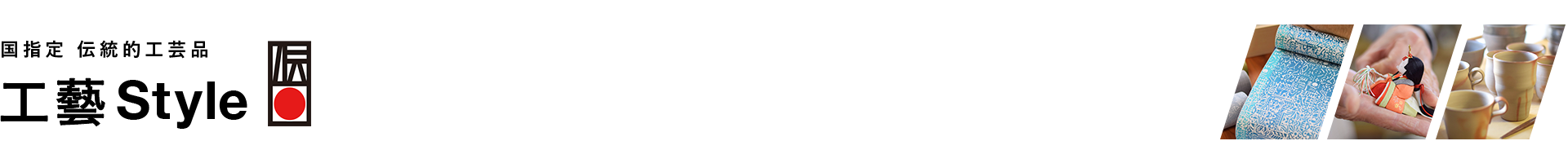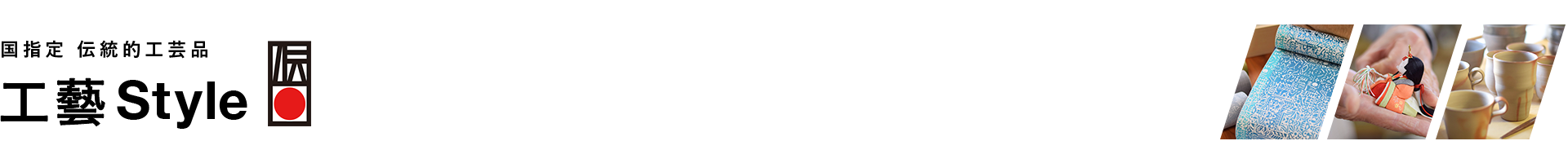山中漆器
16世紀の後半に、良い材料を求めて移住してきた職人集団の人達が行ったろくろ挽きが始まりです。
その技術は山中温泉のあたりに定着し、江戸時代中期には、椀、盆等の日用品の他、温泉にやってきた人々の求めに応じ、土産用の遊び道具を作って売る等、温泉とともに漆器も発展しました。19世紀の前半には塗りの技術や蒔絵の技術が入ってきて、現在の美しい山中高蒔絵(やまなかたかまきえ)の基礎が築かれました。
概要
| 工芸品名 |
山中漆器 |
| よみがな |
やまなかしっき |
| 工芸品の分類 |
うるしの器 |
| 主な製品 |
盆、茶托(ちゃたく)、重箱、茶道具 |
| 主要製造地域 |
加賀市 |
| 指定年月日 |
昭和50年5月10日 |
特徴
非常に細かい縞模様を作り出す「千筋」や「象嵌(ぞうがん)」等の「加飾挽き」の技術・技法を使った作品は、高く評価されています。椀等に見られる、蒔絵の部分が盛り上がっている高蒔絵も山中漆器の特徴です。古典的な味わいに新しい感覚が調和した生活用品として親しまれています
作り方
ゆがみを少なくするため材料となる木を縦方向にとり、ろくろ挽きした後、地の粉を使って整えた下地に、朱色の漆や黒い漆等で上塗りをします。そこに高蒔絵等で飾り付けをします。それぞれの工程は技術を身に付けた別々の職人によって行われます。高蒔絵を施すもの以外に、「加飾挽き」を生かした摺漆(すりうるし)を使って仕上げるものもあります。